戦争中の暮らし
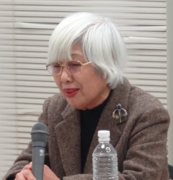
1935年札幌生まれ。作家。
私は生まれは1935年です。国民学校に入ったとき、国民学校制度の二期生でした。学校に上がるのが楽しみで、「学校に行ったら遠足があって運動会があって学芸会があって…」と思っていたのが、入ってみるとそういうことは一切なく、最初にあったのは退避訓練。合図があったら机の下にもぐるとか一列になって逃げるとかそんなことばっかりでした。いつ空襲になるかわからないから家と学校以外にはどこにも行ってはいけないと言われていました。うちにいるのがだんだん苦痛になりましてね。今考えるとあの頃の母親たちはとてもにこにこなんかしていられなかったのではないかと思います。いつ家族が兵隊にとられるかわからないし、いつ空襲が来るかわからない。そういう不安を声に出してはいけない。そういう母親の剣呑な表情を子ども心にいやだなと思っていました。学校に行くとやっとお友だちと楽しくおしゃべりができる。だから私は学校とお友だちが大好きでした。子どもがワイワイいるようなおうちも大好きでしたね。戦争中ですから何回か転校しまして、4つの国民学校に行ったんです。一年生のときにいた杉並の借家は大家さんの家族が満州から引き揚げてくるということで、同じ杉並の天沼1丁目の借家に移りまして、歩いて3分の若杉国民学校に転校しました。そこはまだできたばかりの新しい学校で、校長先生も元気のある人で、うちにいるより学校にいたほうが楽しかった。校長先生がいつも「日本の子どもは優秀だ」というお話をされるのが、私は気が重くてね。言葉遣いや礼儀にもうるさくて、「わたし」と言ってはいけなかった。「わたくし」と言いなさいと。父母のことも「お母さま、お父さま」と呼びなさいと言われまして、私はその頃「おかあちゃま、おとうちゃま」と呼んでいたのですが、おかあちゃまと呼んでも母が聞こえないふりをしていましたね。
学校に行くと女の子同士集まっておしゃべりをする。だれかが「戦争になる前はね」と言うとみんなパアッと顔が明るくなって「うちのお母さんはお化粧してた」「パーマネントをかけてた」「ひらひらのスカートをはいていた」「かかとの高い靴を履いていた」「銀座へ行ってダンスをしたんだって」などと口々に言い出して、お母さんがどんなにきれいで楽し気だったかをうっとりと話していました。今考えるとなんか切ないですね。食べ物の話をしたことなど一回もなかった。結局私たちは目の前にいるお母さんのことしか関心がなかったんですね。授業が始まるとみんなぴっと軍国少女になってちゃんとお務めを果たしていました。道草は絶対いけないと言われていましたが、頭のいい子がいて、出征している兵士のおうちの前に行って最敬礼をして長久を祈るのは道草ではないと言い出して、遠回りしたりしましたね。当時は出征兵士の家とか英霊の家とか表札に書かれていましたから。英霊の家についてはだれかが、「ここの家のお父さんは昼間は靖国神社で白いお着物を着てお仕事をしている。夜の間だけおうちに戻ってくるんだって」という話をききつけ、ひょっとしてまだおうちにいるかもと、垣根の間からのぞいたりしていました。子どもなりになにか楽しみを見つけようとしていたんでしょうね。
本はほとんど手に入らない時代でしたからお友だちの間で貸し借りをしていました。お友だちが30人いれば30冊読めますからね。私の一冊はアンデルセン童話集でした。小学校一年生のときに父が買ってくれた『五粒のえんどう豆』というハードカバーで、私はその一冊を元手にしていろいろな本を借りるわけです。本を持ってない子は自分でノートに絵とお話を書く。それがまた人気があってね。なかなか順番が回ってこなかった記憶があります。クラスの子の本を全部読んでしまって、お隣のクラスの子と貸し借りを始めたら、隣のクラスの担任の先生はこわい男の先生でね。私の本はアンデルセン童話集で外国の本だったので外国の本を読むやつはスパイじゃないかと言われ、没収されました。校長先生もなにかにつけスパイの話をしていましたね。東京に空襲があるのはスパイが情報を流しているからなんだと。私の父は学者で家には外国の本はたくさんあったし、タイプライターもあった。私は、本が没収されたことを親に知られたら怒って学校に乗り込むんじゃないか。そこから親がスパイの嫌疑をかけられたらどうしようとすごく不安で、最後まで本を没収されたことを隠し通していました。
学童疎開で北海道へ
学校で自分のお教室に一歩入ると本当にそこは安心できましたね。教室から一歩外に出るとなにか鎧を着せられたようで、優秀で立派な小国民という顔をしていました。教室の中でだけは安心して先生に甘えていましたね。4回学校を変わりましたがどの担任の先生も女の先生で、母性的といいますか、いやな先生は一人もいなかった。ちょうどその頃学童疎開令が出て、親もいつ離れ離れになるかわからないという気もちがあったのでしょう。箸の上げ下ろしからお掃除からお手伝いから非常にきびしくなっちゃってね。この子一人になってもちゃんとやっていけるようにしなくてはと親はあわててしつけたんたんじゃないかと思うんですけども。3年生になったときに3年生以上は全員学童疎開しなくてはならないことになりました。1学期にお別れ会をしまして、一人ずつ教壇に立ってなにか芸をすることになって、お話する子、歌を歌う子、手品をする子もいて、先生も笑って見ていましたが、今思うと先生もきっとつらかったんじゃないかなと。戦争は絶対にやってはいけないと思っています。
そこで6年生の姉と一緒に母の故郷の北海道札幌へ疎開することになりました。そのときに父が、札幌に行ったら読む本がないだろうと心配して、知り合いのところから名作全集のようなものを譲り受けてきて、「札幌に着いたら読むんだよ」とリンゴ箱に詰めて持たせてくれました。それはうれしかったんですが、私の親は読む本にもうるさくて、中原純一の少女小説などは賢い女が出てこないからダメだ、とか言って読ませてくれなかった。私はこれでうるさい親から離れて好きな本が読めるとうきうきしながら疎開しました。自分も手紙を書きましたし、母からも手紙が来ましたが、母から来た手紙は途中で開封されて検印が押されていましたね。内容も「お隣の何とかさんが南方へ出征されました」「若杉国民学校の校庭に不発弾が落ちました」などというところは朱で消されていました。それを見て私も心配になりましてね。もし私が「家に帰りたい」などと書いたら両親になにか嫌疑がかけられるのではないかと。
札幌の国民学校に入りましたが、担任の先生が優しい先生で毎朝本を読んでくださった。あの頃の先生は教室の中を歩きながら読んでくださったんですね。机と机の間を歩きながら子どもたちの頭をなでたり背中に触ったり。それがまたうれしくてね。おもしろいところにくるとみんなで顔を見合わせて笑ったり、こわいところへくると大げさにきゃーって言ったり、本当に先生が本を読んでくださるというのが最高に楽しいことだった。だから私は読み聞かせっていうのは担任の先生にまず読んでいただきたいと、いつも言うんです。クラスの一人ひとりと目を合わせながら本を読んでくださるとみんなが本を好きになる。掛け算の7の段とか8の段とか少しむずかしいところを、みんなが言えるようになったら残った時間本を読みますと言うと、みんな一生懸命やりました。みんな自分の担任の先生が大好きで学校中で一番素敵だと思っていましたから、それくらい担任の先生との結びつきが今より濃かったんだと思います。先生の目は絶対ごまかせないと思っていましたから、お友だちに意地悪をしたり、うそをついたりはしなかったんだと思います。あのひどい戦争の最中に学校だけは本当に子どもたちを守ってくれたと、私は今でも先生たちを尊敬してるんです。
心の支えになった『綴方教室』
そんな北海道のお教室で先生が読んでくださった本の一つが豊田正子さんの『綴方教室』で、私はそれが楽しみでね。雨が降ろうと暑かろうと「今日は先生は何を読んでくださるのかな」とわくわくして、毎日いやがらずに学校に行ったんです。東京を離れているとやはり東京が恋しかったんですね。『綴方教室』は東京のお話ですから、私はとても親しみを感じましてね。戦争前のお話ですから貧しいけれども自由でのびのびとした暮らしが描かれていました。お金が入ればお米でもお菓子でもなんでも買える。そういう暮らしが私たちのような戦中の子どもにはわからなかったわけです。私は主人公のまあちゃんと心の中で友だちになって、夜眠るときは一緒になって遊ぶ場面を思い浮かべながらいい気分で眠りにつきました。
先生は私たちにも作文を書かせましたが、私は書けと言われればなんだって思い通りにスラスラと書けてしまった。書くことがまったく苦ではなかったんですね。軍国少女ではなかったのに先生が望むようなことをどんどん書けてしまって、それがまたいやだなという気持ちがあった。「綴方教室」のまあちゃんは、自分の思ったことを正直に率直に書いている。それに比べ自分は本当のことを書いていないのではないかという思いがありました。実は後々豊田さんとお知り合いになって仲良くしていただいたんですよ。私が、戦争中豊田さんの作文が本当に心の支えになりましたとお伝えしましたら、豊田さんは「私は作文を、自分を元気づけ、周りの人を元気づけるために書いていたのよ」とおっしゃってました。
戦争が終わり福島へ
4年生の夏に敗戦になりましたが北海道にいて戦争のことはなんにも知りませんでした。東京に空襲があったことも原子爆弾が落ちたことも知りませんでしたね。8月15日、疎開してきていた母と一緒に縁側で天皇陛下の放送を聞きました。私は内容はよくわからなかったのですが、祖母が一言「もう空襲はありません」と言いましてね。そのあと私は原っぱへ行って女の子のお友だちと集まって戦争に負けたと話していたら、だれかが「アメリカ兵というのはとても残酷なんだ」と言い出して、これからどうなっていくんだろうと不安に思いましたね。それから学校へ行くと教科書に墨を塗れと言われまして、今まで空襲になっても教科書だけは持って逃げるように教育されてきたのに、これはどういうことだと子ども心に怒りを覚えましたね。つまり義務教育の9年間の半分、4年半が戦争中で、残りの4年半民主主義の教育を受けることになりました。大人に対する不信感というのは心の中にあったかもしれませんね。
戦争が終わると一家で父の仕事場のある福島に移りました。父は蚕糸試験場で試験官をしていましたので、その官舎に住んでいました。東京は戦後の食糧難でしたが、福島にいたおかげでなんとか自給自足のような形で生活ができました。畑をつくったりヤギを飼ったりしていましたね。福島は戦災を受けていませんでしたから、つつましく心豊かな生活ができてよかったなと思っています。福島の小学校の先生もいい先生でね。戦後の大変なときでしたので一クラスに65人くらいの生徒がぎゅうづめになっていました。中には障がいのある子もいましたが、そういう子にどうやって接するかということを先生が身をもって教えてくれたように思います。だから障がいがあるからといっていじめたりする子はだれもいなくて、とてもよくクラスがまとまっていました。あるときは、ちょっと貧しい家の子に先生が自分の家の草取りを頼んで、そのあとお風呂に入れご飯をごちそうしてあげるというようなこともありました。そういう先生の優しさに私たちもうれしくなってしまいましたね。今も忘れません。今のいじめなどの話を聞くと、先生にそれだけ余裕がないんだなと思いますね。
中学校の図書室での出合い
中学校に入ると、中学校の校舎がまだなくってね。仕方ないので小学校の体育館を板で仕切って教室にして、そこでしばらく勉強していました。そこで新しく民主主義の教育が始まりました。中学校ができるとそこに図書室がありまして、私は本が好きだから毎日図書室に通っていました。ある日そこに『二人のロッテ』がありまして、読んでみたらすごくおもしろかった。それは岩波少年文庫で、きちんとした訳で翻訳本を読ませようという意図をもってつくられたものだから、私が戦中読んでいたような本とはまったくちがうわけです。ケストナーの本というのは、読者との関係が対等なんですよ。相手が子どもだからなどというところは少しもない。ストーリーも親の離婚問題を堂々取り上げていてお父さんは社交的でかっこよく、お母さんは知的な職業婦人、そんなドラマチックな世界に比べると私は本当に平凡な家庭の子どもでつまんないなーと思ったりしていました。それで岩波少年文庫に惹きつけられて、新刊が出るたびに親に買ってもらって、それがこの世界に入る大きなきっかけとなったと思います。なぜあんなふうになにもない中学校に図書室があったかというと、それはGHQが「新制中学校には必ず図書室をおくべし」という方針を出したからなんです。後に岩波少年文庫の生みの親である石井桃子さんとお話する機会があって伺ったら、はじめ少年文庫の企画を出したときに「こんな地味な本は売れないだろう」と上層部は反対したそうです。そこを押し切って発刊にこぎつけたら、日本中の新制中学校が岩波少年文庫を購入してくれて、発刊を続けることができたのよとおっしゃっていました。学校の図書館の力はなんて大きいのだろうと思いましたね。よい本をつくれば売れるというよい時代になったんだと思います。
私は人生の運、不運を左右するものは、どういう人に出会うか、次にどういう本に出合うか、だと思うんですよ。その点私はどちらも恵まれていたなと感じます。学校の図書館の役割も大きいですね。子どもたちの人生の運、不運を決める一つのきっかけになるのですから。岩波がかつて今各界で活躍している方たちに「どこで岩波少年文庫に出合ったか」というアンケートをとったところ、一番多かった答えがやはり中学校の図書室ということでした。ですから学校の図書室というのはぜひ充実してよい本を揃えていただきたいと願っています。
保育士になる決心

私の父は九州の生まれで、北海道の大学に行ったものですから、大家族で育って急に一人で生活しなければならなくなり、次第に一人でご飯を食べることに耐えられなくなって、北海道の家庭学校(今の擁護施設)に転がり込んで、そこに寄宿させてもらって大学に通ったそうです。父は家庭学校で預かられている不良少年たちからも兄さんと慕われて面倒をみていたようで、よく私たち姉妹は「不良少年と同じように育てられた」と冗談を言っていました。家庭学校をつくった留岡幸助先生を父は大変尊敬していました。留岡先生はクリスチャンで、監獄でのボランティアの経験から「やはり子どものころ、家庭でしっかり愛情を注いで育てないとなかなか更生できない」という考えから札幌に「家庭学校」という施設をつくられたようです。留岡先生を尊敬している父の育て方はやはり一本筋の通ったものでしたね。
福島の家のすぐそばには瓜生岩子先生の建てた養護園がありまして、私もよく母のおつかいで果物など持って行ったりしましたが、訪ねてみると子どものいっぱいいる普通のおうちで、なんだか楽しそうでいいなあなんて思っていましたから、そのあたりも私の子どもがたくさんいる環境が好きな原点かもしれないですね。
岩波少年文庫の中に『ジェーン・アダムスの生涯』という本がありまして、ジェーン・アダムスというのはアメリカの女性社会事業家で婦人国際平和自由連盟総裁だそうで、ノーベル平和賞ももらった方ですが、その方の伝記です。それを読んで感動しまして、私もこんなふうな仕事がしたいなと漠然と思ったりしました。また、父の本棚にあった『カン・マルタ』というポーランドの女流作家の本で、お嬢様育ちのマルタが修僧院を出て、しかるべき人と結婚し中流家庭の幸せな新婚生活が始まったのですが、夫が交通事故で死んでしまう。そこでマルタは幼子を抱えて生活していかなければならず苦労していくというお話を読んで、私はけっして花嫁修業なんかするまい、女も仕事を持たなければ!などと強く思っていました。戦後の民主主義の影響で、自立した女になりたいと思っていたんですね。そんなことを思っていたときに、父の本で東京都立高等保母学校のことを知りまして、この学校に入りたいと心に決めていたんです。一家はそのときまだ福島に住んでいましたが、運よくそのときに父が東京に転勤になりまして、この学校を受けることができました。初めて自分で選んで入った学校でしたので勉強もおもしろかった。私は本の中でたくさんの子どもに出会ってるからどんな子どもにあってもびくともしないと自信を持っていたんです。しかし、学校でいろいろな実習や勉強をしていくうちに、病気の子もいれば親のいない子もいる、いろいろな事情の子がいることを初めて実感して、私は何も知らないんだなと恥ずかしく思いました。児童福祉法ができて学校ができて、私は七回生になりますので、日本もやっと福祉に手が回るようになって、学校全体がこれからだという活気に満ちていましたから、とてもいい勉強をさせてもらったと思っています。

